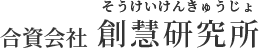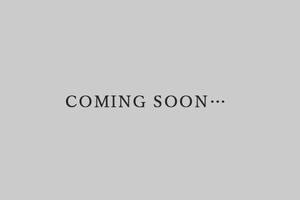従来型経営は終焉 倫理経営に転換せよ、その中にしか活路は無い!
CASE:01 株式会社宮田運輸 代表取締役 宮田 博文様
社会とのつながり
社会的貢献
心を込めて作られた工業製品や農林水産業者からの想いの詰まった生鮮食品や食材を安全・安心・確実に流通させます。
社会的使命
未来世代へ地球環境的問題を残さず、人々の生命線、生活基盤の要であることを強く自覚した運輸業を使命とします。
社会的責任
人々の命と暮らしを守り、社会課題を生まない経営を通じ「良心」を運ぶことに責任を持ちます。
経営の三位一体
目的
誰もが安全・安心ができ、生きる目的と生き甲斐を持てる幸福創造社会の実現をめざす。
理念
「利他の心」を更に磨き、社員の良心に従い「人の道」に適う理念経営の指標に基底し実践する。
使命
人が元来有している子どもの時の「純粋な心」で、互いに響きあい高めあい幸福社会の創造を使命とする。
会社情報
- 業種
- 運送・倉庫全般。
- 業務内容
- 全国に14拠点展開。2013年に自社で起こした交通死亡事故をきっかけにこどもミュージアムプロジェクトを立ち上げ邁進中。

|
コンサルティング前
|
ビジネスモデル構築後(5年後)
|
|
|
従業員数
|
7人
|
8人
|
|
売上高
|
約2億円
|
売上約2億5000万円 粗利益率16%向上(標準化・効率化のため)
|
ヒアリング内容
-
「倫理経営理念」確立(成文化)以前の経営状況
-
10年後のありたい姿
-
「地球倫理」(1994年丸山竹秋/日本的SDGs)への取り組み
-
国連採択SDGs(17目標)への取り組み
-
「倫理経営」推進の現状と今後の展望
「倫理経営理念」確立(成文化)以前の経営状況
経営方針の転換:従業員との思いの共有に向けて
しかし、思いの共有に関して幹部とは、ある程度できたが、それ以外の従業員との思いの共有が中々進まずにいた。
10年後のありたい姿
こどもミュージアムプロジェクト
そして福島復興事業Fukushima22nd CenturyP-roject(22世紀の未来の子供達へ)福島県富岡町へ物流センターを3棟目建築する。福島沿岸地域の物流再構築と雇用促進する。ビバスマイルショッピングモールを建築し福島復興を実現し多様性を認め合う優しい街づくり世界中から訪れたくなる福島に貢献する。愛する従業員と共に誰もが真我で生きられる利他の心が響き合う社会の実現を目指し世界人類が平和で幸せを感じる社会を実現する。
「地球倫理」(1994年丸山竹秋/日本的SDGs)への取り組み
「愛や優しさや思いやり」
国連採択SDGs(17目標)への取り組み
No.8 働きがいも経済成長も。
No.11 住み続けられるまちづくりを。
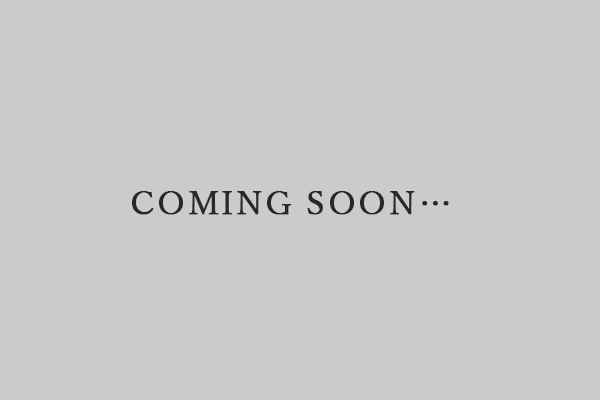
No.17 パートナーシップで目標を達成しよう。
「倫理経営」推進の現状と今後の展望
会社のために人が在るのではなく、人のために在る会社。一人ひとりが持つ良心を人の主体を引き出す場を創り続ける事で、満たされ始めた人が、感謝から生き生きと動き始めている。
従来型経営は終焉 倫理経営に転換せよ、その中にしか活路は無い!
CASE:02 一般社団法人 キャリアエデュケーション協会代表理事 山下エミリ様
社会とのつながり
社会的貢献
次代を担う賢く幸せな子どもを育てる母親に「母親の在り方」「生き方」「正しい子育て」を説き、母なる女性としての自立と生涯現役を支援する
社会的使命
「子育て」というかけ甲斐のないキャリアを積んだ女性が、それを最大限に活かして精神的・経済的に自立し輝ける社会創りに貢献できるように支援する
社会的責任
「子育て」中の母親が持つ様々な問題に寄り添い、自ら開発し実績を積んできたメソッドを活用し「子どもの心を育む」ための課題解決に責任を持つ
経営の三位一体
目的
核家族化や分断が増える社会の中で、次代を担う子ども達が自分らしく輝くための「抱擁力のある社会づくり」を目指す
理念
自社開発のメソッドに込めた理念を「抱擁力のある社会づくり」を実践する人材の育成を社会への普及・浸透を図る
使命
子育て中の母親には「正しい母親の在り方と子育て」を伝承し、子離れした母親には自主自立のための智慧と環境を提供する
会社情報
|
コンサルティング前
|
ビジネスモデル構築後(5年後)
|
|
|
従業員数
|
7人
|
8人
|
|
売上高
|
約2億円
|
売上約2億5000万円 粗利益率16%向上(標準化・効率化のため)
|
ヒアリング内容
-
「倫理経営理念」確立(成文化)以前の経営状況
-
10年後のありたい姿
-
「地球倫理」(1994年丸山竹秋/日本的SDGs)への取り組み
-
国連採択SDGs(17目標)への取り組み
-
「倫理経営」推進の現状と今後の展望
「倫理経営理念」確立(成文化)以前の経営状況
倫理経営の軸:負担軽減から新たな展開への道
10年後のありたい姿
美賢女メソッド:子育てとキャリアの融合から生まれる幸せな未来
「地球倫理」(1994年丸山竹秋/日本的SDGs)への取り組み
環境保護とペーパーレス手続きの先進
国連採択SDGs(17目標)への取り組み
No.4 美賢女メソッドの認知活動。
No.5 子育て後の女性に仕事の提供。
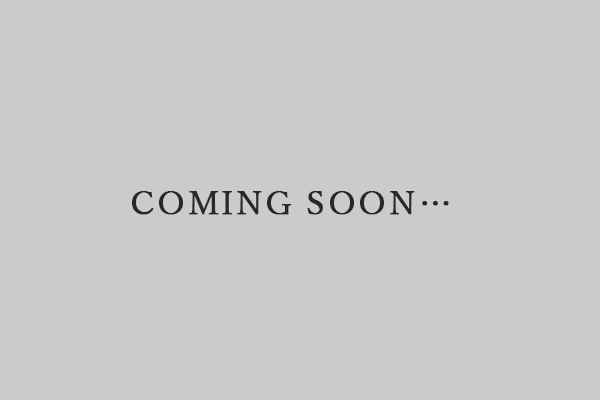
No.16 心理療法が有効な認知活動。
「倫理経営」推進の現状と今後の展望
従来型経営は終焉 倫理経営に転換せよ、その中にしか活路は無い!
CASE:03 TOMA100年企業創りコンサルタンツ株式会社 代表取締役 藤間 秋男様
社会とのつながり
社会的貢献
100年越え企業が3万社以上という世界一の日本企業永続性を今後も持続するため、あらゆる事業継承問題を解決する
社会的使命
中小企業事業永続性の要である「後継者問題による廃業」を防ぎ、技術や技能の継承とその雇用を守る。
社会的責任
日本の基盤を支える中小企業、その次代を創る事業継承者の育成、経営理念の継承等を包括的に支援する
経営の三位一体
目的
日本経済産業を下支えしている中小企業の永続化を「100年企業創りコンサルティング」を通じ元気な100年企業創りを支援する。
理念
「明るく、楽しく、元気に、前向きに」を基底に、永続的事業継承のための事業後継者育成委支援を理念とする。
使命
中小企業の事業後継者問題を解決し日本一たくさんの「100年企業」を創り続ける会社となる。
会社情報
|
コンサルティング前
|
ビジネスモデル構築後(5年後)
|
|
|
従業員数
|
7人
|
8人
|
|
売上高
|
約2億円
|
売上約2億5000万円 粗利益率16%向上(標準化・効率化のため)
|
ヒアリング内容
-
「倫理経営理念」確立(成文化)以前の経営状況
-
10年後のありたい姿
-
「地球倫理」(1994年丸山竹秋/日本的SDGs)への取り組み
-
国連採択SDGs(17目標)への取り組み
-
「倫理経営」推進の現状と今後の展望